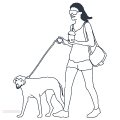犬を飼い始めて、1番最初に悩むのが「しつけ」ではないでしょうか?
正しい「しつけ」を行わなければ、問題行動を起こし周囲に迷惑をかけてしまう可能性もあります。
犬と一緒に快適な共同生活を送るためには、飼い主さんが正しいしつけを行うことが重要です。
そこで、今回は基本的なしつけやしつけの必要性、しつけを行う時のポイントなどを詳しく紹介します。
この記事を読んでわかるポイント
- 犬のしつけの必要性がわかる
- しつけを始めるタイミングと注意点がわかる
- 基本的なしつけの方法がわかる
【Contents】
しつけの必要性

犬と人間が幸せに、快適な生活を送るためには「しつけ」が重要なポイントです。
犬に正しいしつけを行うか行わないかで、これからの日常生活が大きく変わります。
ここでは「なぜしつけが必要なのか」を具体的に紹介していきます。
3つの理由
- 犬を守るため
- 他人を守るため
- 行動範囲を広げるため
1.犬を守るため
しつけは、犬を危険から守るために必要なことです。
行き過ぎたしつけは必要ありませんが「しつけはかわいそう」「自由に育てたい」というのは少し違います。
もちろん「自由にのびのび暮らしてほしい」という気持ちもわかります。
しかし、人間社会と一緒に生活していくには「最低限のしつけ」を覚えさせる必要があります。
例えば、愛犬と散歩している時に道路に飛び出しそうになった場合、飼い主さんの「待て」の指示を聞くことができれば事故を防げます。
このように「しつけ」は、愛犬を危険から守る大切なことなのです。
2.他人を守るため
周囲の方すべてが、犬が好きなわけではありません。
犬アレルギーの方や小型犬でも怖いという方も多くいます。
そういった周囲の方々に、最低限迷惑をかけないようにするのが「飼い主さんの役目」
犬も周囲の方々も、みんなが快適な生活おくるためには、犬に正しい「しつけ」を行うことが必要です。
3.行動範囲を広げるため
しつけをしていない犬は、いたずらや無駄吠えをしてしまう時があります。
それでは安心して、一緒に色々な場所に連れて行くのは少し難しいでしょう。
しかし、しっかりと犬にしつけを行っていれば、安心してお出かけすることができます!
ドッグカフェやドッグラン、愛犬と一緒に宿泊できる旅館もあります。
愛犬とたくさんの思い出をつくるために「正しいしつけ」を行いましょう!
いつからしつけを始めればいいか

「しつけはいつから始めればいいの?」と疑問に感じている方も少なくないでしょう。
犬にしつけを始めるタイミングは、子犬の頃から行えるので飼い主さん次第です。
そこで、ここからは「時期別」にしつけを行うポイントを紹介します!
基本は犬を迎えた初日から
基本的には、犬を家に迎えた日からしつけを行います。
しかし、最初から「おすわり」や「お手」を覚えさせるのではなく、まずは家の環境に慣れさせてあげることから始めましょう。
例えば「家のチャイムの音・掃除機の音・生活音」を聞かせて日常の音に慣れさせます。
また、音慣れトレーニング用のCDなどを購入し、それを活用するのもおすすめです。
少しずつ環境に慣れてきたら、たくさん名前を呼んで犬の名前を覚えさせましょう。
そして、ワクチン接種が済んでいれば、周囲の人にたくさん身体を触ってもらい、身体に触れられることに慣れさせます。
ここで重要なのが、絶対に無理に行わないことです。
子犬の頃の記憶は鮮明に記憶に残りやすいため、楽しく遊びながら触れ合いましょう!
まだ犬の名前が決まっていないという方は、下記の記事に「愛犬の名前の付け方とランキング」を掲載しているので、参考にしてみてはいかがでしょうか?
-

-
参考【愛犬に素敵な名前を】犬の名前の付け方と人気名前ランキングを紹介
犬を家族に迎え入れて、1番最初にしなければならないことは「犬の名前」を決めることです。 名前を決めてあげないと、犬を自治体に登録することも、犬を呼んであげることもできません。 犬の命名は「最初の贈り物 ...
続きを見る
生後~生後3ヶ月
犬が生まれてから生後3カ月までの、社会準備期間のことを「社会化期」といいます。
この期間に、親犬や兄弟と一緒に過ごすことで、犬同士での遊び方・噛む力加減などを学びます。
好奇心旺盛で、たくさんのことを吸収できる時なので、さまざまな経験をさせるいい時期です。
そのため「生後3ヶ月過ぎた犬を迎え入れる方がいい」といわれるのは、上記のような理由からでしょう。
生後3ヶ月以降
生後3ヶ月を過ぎたら、基本的なしつけを行います。
まずは「おすわり」「お手」「待て」など、よく使うものから教えましょう。
この時期に重要なポイントは「短時間で楽しく」しつけを行うこと!
犬も人間と同様に、楽しくないことを長時間ずっと指示されるのは、嫌な気持ちになり飽きてしまいます。
そのため、飼い主さんは叱らず、心にゆとりをもってしつけを行いましょう!
成犬
基本的なことができるようになったら「食事・散歩・トイレ」のしつけなどを行いましょう!
また、成犬からしつけを始めるという方も遅くはありません!
子犬よりは、しつけに時間がかかってしまいますが、根気強くじっくり時間をかけて行いましょう。
無駄吠えや甘噛み・気になる問題行動を起こしてしまう場合は、早急な対処が必要です。
しつけを行う時の注意点

飼い主さんがなんとなく適当に、しつけを行うと犬は混乱して覚えることができません。
そのため、まずは飼い主さんが「しつけのルール」を作る必要があります。
そこで、ここではしつけを行う時に「抑えておきたい4つの注意点」を紹介します。
4つの注意点
- 注意や指示する時の用語は統一させる
- 人によって犬に対応を変えない
- 大げさに騒がない
- いたずらをさせない環境作りを行う
1.注意や指示する時の言葉は統一させる
犬がいたずらをした時などに「ダメ」「いけない」「NO」などと、その度に使用する言葉が変わると犬が混乱してしまうので、言葉は統一させましょう。
また、言葉は簡潔に伝えることが大切です。
例えば「ダメダメ」「しちゃいけないよ~」など、曖昧な言葉は犬には通じません。
そのため「ダメ!」と短く簡潔に伝えることで、犬は理解できるようになります。
家族で使用する言葉が、バラバラにならないよう統一させましょう。
2.人によって犬に対応を変えない
無駄吠えや甘嚙みをした時、お母さんは注意するけどお父さんはしないということはありませんか?
人によって犬に対応を変えてしまうと、犬は良し悪しがわからなくなってしまいます。
そのため、しつけを行う前に「家庭内での生活のルール」は統一させておきましょう!
3.大げさに騒がない
犬がいたずらなどをした時に、叩いて注意したり、大声で叱るのは絶対にやめましょう。
飼い主さんが大きな声を出すことで、犬は「構ってもらえた」と勘違いして、わざと同じ行動を繰り返してしまう可能性があります。
また反対に、飼い主さんに恐怖心を感じて、隠れて同じ行動をとる場合も・・・
そのため、しつけを行う時は上手にできた時はたくさん褒めて、注意する時は短く簡潔に「ダメ」と伝えましょう。
4.いたずらをさせない環境作りを行う
飼い主さんが、犬に「いたずらされたくない物は高い場所に置く」「家の中で入ってほしくない場所には塀を設置する」など、いたずらをさせない環境作りを行いましょう。
また、犬が誤飲してしまいそうなサイズの物は、危険なので片付けておきましょう。
トイレのしつけが完璧ではない犬は、トイレマット・玄関マット・お風呂マットなどを、トイレシートと勘違いしてしまう場合があります。
粗相をさせたくない場合は、トイレのしつけが終わるまでは、マット類は片付けておいた方がいいでしょう。
まずはこのしつけから始めよう!

しつけを行う時に、まず教えておきたいのは「アイコンタクト」と「身体に触れられることに慣れさせる」ことです。
この2つができるようになれば、他のしつけもスムーズに行えるようになるでしょう。
飼い主さんとのアイコンタクトをとれるようにする
アイコンタクトとは、目と目を合わせることで、しつけを行う時に基礎になるものです。
しつけを始める時は、まずこの「アイコンタクト」から始めましょう。
アイコンタクトのしつけ方は、以下の手順を参考にしてください!
しつけの手順
- 愛犬の名前を呼び振り向かせる
- 目が合ったらすぐに褒めてご褒美をあげる
- 数秒間目を合わせる
- 上記の3つを繰り返し行い徐々に目を合わせる時間を長くする
アイコンタクトを覚えさせるためには「アイコンタクト=褒められる・良いこと」と認識させることが大切です。
また、ご褒美としておやつを使用する場合は、おやつを持っている手を飼い主さんの顎の下に持ってきて、愛犬の名前を呼ぶと効果的です。
アイコンタクトを覚えさせることで、犬の意識を飼い主さんに向けることができるため、効果的にしつけを行うことができます。
身体に触れられることに慣れさせる
シャンプー・爪切り・ブラッシングなどのケアをする時、触れられるのに慣れていないと、暴れて怪我をしてしまいます。
また、外出した時に急に犬を撫でてくる人がいたり、小さい子が近寄ってくる場面も多くあります。
そんな時に、身体を触られることに慣れていないと、吠えたり噛みついたりしてしまう可能性も・・・
その他にも、動物病院を受診する時に暴れてしまい、スムーズに診察が行えないということもあります。
色々なトラブルを避けるためにも、子犬の頃からたくさん撫でてあげ、身体を触られることに慣れさせていきましょう!
しつけの手順
- まずは優しく撫でてリラックスさせてあげる
- 飼い主さんの手を軽く握りしめて甲の部分を犬の鼻にゆっくり近づける
- 手のにおいを嗅いでくれたら顎の下から首を優しく撫でてあげる
- 少しずつ慣れてきたら犬が嫌な箇所(足先・口・お腹・耳・お尻・尻尾)を触る
- 徐々に触る時間を増やしていく
急いで無理やり触ってしまうと、犬は恐怖心を感じるようになってしまいます。
飼い主さんもリラックスした状態で、犬に声をかけながら少しずつ触ってあげましょう!
【基本のしつけ】1.トイレを教える

生後2~3ヶ月経過すると、トイレを覚えれるようになります。
しかし、トイレのしつけは簡単なようで実は難しい・・・
すぐに覚えられることではないので、じっくり時間をかけて教え込みましょう!
ここでは、トイレを教える手順と注意点を紹介します。
犬にトイレを教える方法
犬にトイレのしつけを行う時に「何から始めればいいのかわからない」という方も多いでしょう。
そんな方のために、ここでは犬にトイレを教える方法を詳しく紹介します。
トイレのしつけを行う方法
- 犬が眠る場所とは別の場所にトイレを設置する
犬の本能的に寝床で排泄することを嫌うため、眠る場所とトイレの場所は別の場所に設置しましょう! - 犬のトイレタイムに誘導する
ソワソワする仕草を見せたり、床の匂い嗅ぎ始めると、犬の排泄のサインなのでその都度トイレに誘導してあげましょう。
また、食後や起床時、運動後なども排泄しやすいタイミングです。 - 犬がトイレを探し始めたら誘導する
くるくる回る仕草をしたり、お尻を床に引っ付けたりするポーズを取り始めたら「待って」と声をかけましょう。
そして、すぐにトイレへと誘導しましょう。 - 正しい場所で排泄ができたら褒める
誘導を繰り返し行うと少しずつ場所を覚えるようになります。
正しい場所で排泄ができたら、たくさん褒めてあげご褒美をあげるようにすると「トイレ=良いこと」と覚えるので、これからトイレでしてくれるようになります。
3つの注意点
上記のトイレを教える手順を行う時に、必ず注意してほしい「3つの注意点」があります。
できるだけ早くトイレを覚えてもらうために、この3つの注意点をしっかり抑えておきましょう!
3つの注意点
- 失敗しても叱らない
- 失敗したら徹底的に消臭を行う
- トイレの場所は固定する
1.失敗しても叱らない
犬がトイレを失敗してしまっても、絶対に叱ってはいけません。
犬は叱られたことにより「違う場所にしたから怒られた」という認識ではなく「排泄したから怒られた」と誤解してしまう場合があります。
そのように認識してしまうと、隠れて排泄するようになったり、排泄自体が嫌になってしまいます。
また、失敗した排泄の掃除は何も言わず淡々と片付けるようにしましょう。
2.失敗したら徹底的に消臭を行う
トイレの場所を臭いで覚えている場合が多いので、場所を間違えて排泄してしまった場合はすぐに掃除をして、排泄の匂いは徹底的に消しましょう。
反対に、排泄を拭いたティッシュなどをトイレに置いておくと、自然とトイレの場所を認識するようにもなります。
3.トイレの場所は固定する
早くトイレを覚えさせたいからといって、トイレの場所を色々試すのはよくありません。
場所が変わると犬も混乱してしまい、わからなくなってしまいます。
そのため、一度決めたトイレの場所は動かさずに固定しましょう!
【基本のしつけ】2.散歩のしつけ

犬にとって散歩は、運動する場でもあり社会のルールを学ぶ場でもあります。
社会のルールを守れなければ、犬同士のトラブルや他人に危険を及ぼす可能性があります。
そのようなトラブルを避けるため、散歩のしつけを行うことはとても重要です!
また、犬が外に散歩に行くことができるのは、ワクチン接種が終わってからになります。
いつから散歩デビューしていいのか、獣医師と相談しましょう!
ここからは「犬に散歩のしつけを行う方法」を紹介します。
散歩のしつけを行う方法
- 抱っこから始める
- 首輪とリードに慣れさせる
- リードを引っ張らせない
- 人や犬に吠えさせないようにする
1.抱っこから始める
初めて道路を歩く時は緊張して怖がってしまうので、まずは飼い主さんが抱っこしてあげましょう。
最初の散歩は、犬が安心できるように人通りが少ないところや車が通らない静かな場所を選んでください。
犬の様子を見ながら、慣れてきたら徐々に散歩の時間と距離を長くしていきましょう。
首輪とリードに慣れさせる
散歩デビューの時に初めて首輪やリードをつけられると、ビックリして嫌がってしまう場合があります。
首輪やリードを慣れさせるために、室内で遊んでいる時から首輪をつけたり、家の中でリードをつけて歩く練習などをするといいでしょう。
愛犬に適しているリードの選び方を知りたいという方は、以下の記事を参考にしてみてはいかがでしょうか?
-

-
参考人気犬用リード8選を徹底比較!利用者の口コミや特徴も詳しく紹介
愛犬の散歩に必要なアイテム「犬用リード」 犬用リードには「機能性」「デザイン性」などに、特化したたくさんの種類があるので、選ぶのに迷ってしまう飼い主さんも多いのではないでしょうか? そこで今回は、犬用 ...
続きを見る
リードを引っ張らせない
犬との理想的な散歩は、飼い主さんと隣同士で歩調を合わせて歩くことです。
犬が飼い主さんの前後を歩いている場合は、軽くリードを引っ張り、飼い主さんの隣に歩くことを覚えさせます。
万が一、犬が隣に来ない場合はアイコンタクトをしたり、おやつなどのご褒美を与えてみましょう。
人や犬に吠えないようにさせる
道端ですれ違う人や犬に吠えてしまう場合は、おやつや飼い主さんが声をかけて、気を紛らわせてあげましょう。
また、犬は縄張り意識が強いため、毎日同じ散歩コースを歩いていると、自分の縄張りだと勘違いしてしまいます。
すれ違う犬に吠えている時は、自分の縄張り入られたと思って吠えている可能性があります。
そのような場合には、日替わりで散歩コースを変えてみましょう。
【基本のしつけ】3.食事のしつけ

食事のしつけは、犬の健康維持のためにとても大切なことです。
しかし、犬がフードを欲しがっているからといって、自由に与え続けていると肥満や生活習慣病になる危険性があります。
また、それだけではなく食事の執着が強くなりすぎてしまい、床に落ちているものまで食べてしまう場合も・・・
そのようなことにならなためにも「食事をとる時は飼い主さんの許可が必要」だということをしつけましょう。
ここからは、食事のしつけを行う方法を紹介します。
食事のしつけを行う方法
- 「まて」「よし」ができたら食事を与える
- フードを奪わず追加する
- 人間の食事を与えない
1.「まて」「よし」ができたら食事を与える
フードを見ると、犬は嬉しくなって興奮状態になってしまいます。
しかし、興奮状態のままフードを与えると、喉を詰まらせてしまう危険性があります。
そのため、一度落ち着かすために「まて」をさせましょう。
指示通り「まて」ができたら「よし」と言って、フードをすぐに与えてください。
すぐに「よし」と言わず「おあずけ」をしてしまうと、犬と飼い主さんの信頼関係が失われたり、フードへの執着心がさらに強くなってしまうのでやめましょう。
2.フードを奪わず追加する
犬は自分のフードを守る習性があるので、飼い主さんがフードボウルを触ろうとすると、威嚇してきたり噛みついてしまう場合があります。
「食事は守らなくてもいい」と覚えさせるために、フードを食べている途中に、犬が大好物なものを追加してあげましょう!
そうすることで、フードをとられる警戒心が少なくなっていきます。
3.人間の食事を与えない
家族が食事を行っている時に、とても欲しそうな眼差しで目を見つめてくる時があります。
筆者の愛犬も、横に座ってずっと訴えかけてくるので、何度も誘惑に負けそうになったことがあります。
しかし、そこで人間の食事を与えてしまうと「こうするともらえるんだ」と覚えてしまいます。
人間のご飯は、犬にとって身体にいいものばかりではなく、害を与えるものもたくさんあります。
犬の健康を考えて、人間の食事は与えないようにしましょう!
犬に安全性の高いドッグフードを与えたいと考えている飼い主さんは、以下の記事を参考にしてみてはいかがでしょうか?
-

-
参考【おすすめ11選】愛犬に食べさせたい安全な国産ドッグフードを紹介
犬が健康で長生きするためには、適切な運動や食事が大切です。 とくに、食事内容は犬の健康に直結するものなので、安全で栄養のあるドッグフードを選ぶ必要があります。 しかし「数多くあるドッグフードの中から愛 ...
続きを見る
【基本のしつけ】4.吠え癖・噛み癖のしつけ

犬の吠え癖・噛み癖は、快適に共同生活を送るためにとても大事なしつけです。
吠え癖がついてしまうと、近隣トラブルになりかねません。
また、嚙み癖がついてしまうと、家具や家の大切な物を破損させてしまう場合もあります。
子犬の頃は、かわいくてなんでも許してしまいそうになりますが、子犬の頃からしつけることが肝心です!
ここからは、吠え癖・噛み癖をしつける方法を紹介します。
吠え癖・噛み癖のしつけを行う方法
- 要求吠えに反応しない
- 叱る時は声色を変える
- 噛んでもいいおもちゃを与える
1.要求吠えに反応しない
「遊んでほしい」「ご飯が欲しい」など、飼い主さんに何かを求めている時に吠えている場合があります。
しかし、その時に「吠えないで!」と言っても、叱られているとは理解できずに「構ってもらえた」と勘違いしてしまうことがあります。
1度注意しても聞かないようなら、無視してみるのも1つの手段です。
2.叱る時は声色を変える
言葉が理解できない犬に、いつもの声色で叱っても、わかってくれない時があります。
そんな時は、いつもより低めの声で叱ってみましょう。
しかし、叱る言葉は変えずに「ダメ」と短く簡潔に伝えることが大切です!
3.噛んでもいいおもちゃを与える
犬は歯の生え変わりの時期に、どうしても何かを噛みたくなってしまいます。
そんな時は、叱らずに嚙んでもいいおもちゃを与えてあげましょう。
そして、おもちゃを噛むようになったら、たくさん褒めてあげてください。
そうすることで「おもちゃを噛むと褒めてもらえる」と認識して、他の物を噛まなくなるでしょう。
以下の記事では、筆者がおすすめしたい「人気おもちゃ10選」を紹介しています!
-

-
参考【徹底比較】犬が喜ぶ人気おもちゃ10選!特徴や口コミも紹介
犬用おもちゃは「しつけ」や「留守番の暇つぶし」などに役立つアイテム。 おもちゃで遊ばせることで、運動不足が解消されたり、ストレス発散にもなります。 昨今、犬用おもちゃは数えきれないほどの種類があり、ど ...
続きを見る
犬と人間お互いのために「しつけ」をしよう!

おさらい
- しつけは犬と人間お互いのために必要
- しつけは根気強く少しずつ行う
- 褒める時・叱る時のメリハリをつける
犬のしつけは、飼い主さんと犬がこれから幸せに暮らしていくために、絶対に欠かせないものです。
始めはうまくいかないことも多いかもしれませんが、少しずつ焦らずにしつけを行いましょう。
万が一、犬のしつけに不安がある方は、犬のしつけ教室やドッグトレーナーの方に、相談してみるのも1つの方法です。
正しいしつけ方のポイントを抑えて、愛犬と楽しい生活を送りましょう!