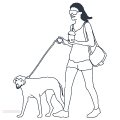家族に迎え入れた愛犬や愛猫は、とても大事でかけがえないのない存在ですよね。
ペットが元気な時はずっと一緒にいられる気がしてしまいますが、いつか来るお別れは避けられない事実です。
筆者も今までに犬や猫、ハムスターを飼っていたので、何度もお別れを経験してきました。
一緒に過ごした日々を思い出すと、今でも後悔や寂しさが溢れだしそうになります。
しかし、ペットのお別れに向き合い、時間をかけながら乗り越えるしかないのです。
今回は、ペットロスの症状やペットロスの乗り越え方、周囲の人の接し方について紹介していきます。
この記事を読んでわかるポイント
- ペットロスの症状がわかる
- ペットロスになる原因がわかる
- ペットロスになりやすい人の特徴がわかる
- ペットロスを重症化させないための予防策がわかる
【Contents】
ペットロスとは?

家族である大切なペットを亡くした喪失感や深い悲しみのことを「ペットロス」といいます。
ペットロス自体は珍しいことではなく、ペットを飼っていたことがある方なら誰しも経験するでしょう。
個人差はありますが、数週間から数カ月経つと少しずつ立ち直る方が多いですが、なかには重症化して体調や日常生活にも支障をきたす場合があります。
上記のように、抜け出せず重症化してしまったことを「ペットロス症候群」と呼ばれることもあります。
ペットロスになる原因

ペットロスになる原因には、ペットとの関わり方や周りの環境などが関係しています。
上手に付き合っていくためには、抜け出せない原因を探ることが大切です。
以下では「ペットロス」になる原因を紹介するので、現在の自分に当てはめて考えてみましょう。
心構えができていなかった
不慮の事故や前触れのない死、ペットの死はどんな別れ方でも非常に辛く悲しいものです。
しかし、そのなかでも「突然の別れ」は飼い主さんの心構えができていないので、大きなショックから陥りやすいといわれています。
現実を受け止めらず納得できない別れ方に、亡くなってしまった原因を自分自身のせいだと思い込む方が多く、さらに拍車をかけてしまいます。
周りに悲しみを共有できる人がいない
ペットが亡くなった時の深い悲しみは、実際にペットを飼った経験がある人にしかわかりません。
相談した相手によっては「たかがペットでしょう」と心無い言葉をかけられて、さらに辛い思いをすることもあるでしょう。
大事なペットと一緒に過ごした日々を思い返すと「たかがペット」という言葉だけでは片付けることはできないですよね。
今はインターネット社会なので、SNSや掲示板などを活用して同じ境遇の方達を探すことができます。
同じ悲しみや苦しみを味わった方たちに、自分の気持ちをさらけ出すことで、少しは心が落ち着くでしょう。
周囲に悲しみを共有できる人がいない人は、ぜひ上手にインターネットを活用することをおすすめします。
ペットがいない時間の過ごし方がわからない
毎日ご飯をあげて散歩に連れて行き、たくさんペットに愛情を注いできたことでしょう。
そんなペットがいなくなると、時間の過ごし方がわからなくなって、現実を突き付けられたような気持ちになります。
筆者も愛犬とお別れした時、愛情の注ぎ口を失い、この寂しさをどこに向ければいいのか戸惑いました。
家族も同じように深く悲しんでいたので、みんなが少しでも元気が出るように、メモリアルグッズを作りました。
悲しみは消えることはありませんが、飼っていた愛犬を身近に感じられることで少し心が和んだのでおすすめです。
 責任を感じ後悔している
責任を感じ後悔している
ペットの病気に気付けなかったり、不慮の事故に巻き込まれて亡くなった場合、自分の責任だと後悔してしまうでしょう。
自分を責め続けて後悔する毎日が続きますが、謝る相手はもういません。
飼い主さんのことを大好きなペットは、飼い主さんを責めないし悲しんでいる顔を見たくないはずです。
写真の前で目を閉じて、心の中でペットへの愛情や想いを伝えてあげましょう。
思いっきり泣けていない
目の前の状況を理解できず、涙が出てこない時ありますよね。
しかし、涙をたくさん流して感情を素直に表現することで、乗り越えられる悲しみもあります。
泣けない人には「人がいると泣けない」「この場所では泣けない」「まだ実感がわかない」など、さまざまな理由があるでしょう。
感情を吐き出すためにも、愛犬とのお別れを受け入れられるようになった時には、1人で思いっきり泣ける時間を作ることをおすすめします。
火葬やお葬式に立ち会ってあげれなかった
人間のお葬式には会社や学校を休んででも参列しますが、ペットのお葬式は休む理由として認められない場合があります。
お葬式はお別れの儀式なので、お別れをするための心の準備であり、それを行うことで心の整理ができるのです。
筆者も愛犬を火葬してお骨になって帰ってきた時、やっと現実を受け止めるしかないのだと思いました。
しかし、火葬やお葬式に立ち会えなかった方は、まだどこかに愛犬がいるような気がして、悲しみの渦から抜け出せなくなることも多いようです。
ペットロスの症状【精神・身体】

ペットロスになると、精神的・身体的どちらにも症状がでる可能性があります。
とくに精神的な不調に陥いってしまう方が多く、人によっては「うつ病」を発症してしまう場合もあります。
以下では、具体的にどんな症状がでるのか紹介していきます。
精神的な症状
ペットロスになると、以下のような精神的症状があらわれます。
精神的な症状
- 喪失感や孤独感が付きまとう
- 集中力が衰える
- なにをしている時も楽しくない
- 愛犬の遺品整理ができない
- 急に不安に襲われる
- いないはずのペットの姿が見える
- 物事に対して悲観的な考えしかできなくなる
上記の症状が続くと、心に余裕がなくなりお酒やタバコの量が増えたり、家族と喧嘩をしたりと、長い目で見ても健康やメンタル面で悪い影響を及ぼします。
身体的な症状
ペットロスになると、以下のような身体的症状があらわれます。
精神的な症状
- 夜寝つきが悪くなり眠りが浅くなる
- ふとした瞬間に涙がでる
- 食欲がなくなる
- 食べ物の味を感じなくなる
- つねに倦怠感がある
- 体重が急激に減少・増量する
- 下痢や嘔吐を繰り返す
- 蕁麻疹などの皮膚に不調がでる
- 肩凝りがひどい
- 身体がしびれてくる
- 眩暈がおこってフラフラする
症状は個人差があるので、上記に挙げたものが全てではありません。
これらの症状は時間が経てば徐々に軽くなっていくことが多いですが、さらに悪化してしまう場合もあります。
そのような場合には、カウンセリングや病院に行って、周囲のサポートを受けるようにしましょう。
ペットロスになりやすい人の特徴

現在苦しんでいる方やこの先ペットとお別れした時ペットロスになりそうで不安に感じている方もいるでしょう。
重症化を防ぐためには、ペットロスになりやすい人の特徴を知っておくことが大切です。
以下の特徴が自分に当てはまっているなと感じる方は、下記で紹介する「3つのペットロス対策」を必ず読みましょう。
後悔することが多く自分を責めてしまいがちな性格
普段の生活から「あの時こうすればよかった」と後悔したり、自分を責めてしまいがちな性格の人は、自責の念から苦しんでしまう傾向にあります。
上記のような性格の人は、思いやりがあり優しい心の持ち主なので、常に相手の気持ちを考えて行動する人が多いです。
そのため、ペットの死に対しても「自分が悪い」と自分を責めて深く後悔します。
誰でも後悔することはありますが、必要以上に思い込みすぎないようにしましょう。
1人暮らしでペットだけが話相手だった
実家から出て1人暮らしを始めた人が、寂しさを紛らわすためにペットを飼いはじめることが多いです。
1人暮らしだと話す相手もいないので「ペットだけが話相手」だという人少なくないでしょう。
そんな大事なペットがいないことの現実が受け止められず、ペットロスに陥ってしまう人がいます。
ペットと長い期間一緒に過ごしてきた
ペットと一緒にいる時間が長いほど、その分愛情が大きくなります。
大切な思い出や一緒に過ごしてきた時間が長いほど、ペットを失った時の喪失感は大きいでしょう。
寿命が近づいてきているなら受け入れたくない事実ですが、少しずつ心構えをするようにしてください。
感情の起伏が激しく世間体を気にしてしまう人
感情の起伏が激しい人は、時々ペットを思い出して痛烈な悲しみを覚えます。
そのような人はショックが尾をひきやすく、ペットロスになりやすいといわれています。
また「ペットが亡くなったくらいで仕事を休むわけにいかない」「ペットが亡くなったから泣くのは男らしくない」など、世間体や常識に囚われやすい人も要注意。
必要以上に長引かせないためには、自分の感情に素直になり思いっきり泣くことが大切です。
一般的に日本人男性は「泣く姿を見せることは恥ずかしい」「悲しみを表現することは男らしくない」とされることが多いので、悲しみを内に秘めてしまう傾向にあります。
ペットが亡くなった時は、そのような世間体や常識に囚われずに思いっきり泣きましょう。
ペットとの愛着関係が深かった人
ペットとの愛着関係が深ければ深いほど、飼い主さんはペットロスに陥りやすい傾向にあります。
あなたとペットの関係について、下記の項目がどれくらい当てはまるか確認してみましょう!
あなたとペットの関係チェックリスト
- 家族の中で1番ペットに懐かれている
- どんなに忙しくてもペットとの時間を確保している
- 帰宅した時、1番に自分のところへ走ってくる
- たわいもないことでもペットに話すことが多い
- 辛い、悲しい時はペットと触れ合うことが多い
- ペットは自分が嬉しい時や悲しい時の気持ちの変化に気付いてくれる
- ペットは自分の言うことをよく聞く
- ペットは自分が移動するたびに後ろをついてくる
- 友人や職場の人にペットの写真をよく見せる
- ペットが近寄ってきた時は無視することはなく構ってあげる
- ペットにプレゼントを買うことがある
- 他の人といる時間よりペットといる時間が好き
- ペットが自分を困らせることは少ない
- ペットは大事な家族の一員だと思っている
- 寝る時は同じ部屋、布団で寝ている
- TVや本を見ている時でもペットは視界に入る場所にいる
上記の項目に当てはまる数が多いほど、ペットとの絆は深いといえます。
ちなみに筆者は、ほぼ当てはまっていたので気を付けないといけないと感じました。
ペットロスを克服するためのプロセス

克服するためには「5つの克服プロセス」があります。
5つの克服プロセス
- 拒否
- 怒り
- 交渉
- 悲しみ、抑うつ
- 受容、回復
以下のことを参考に、ペットロスに苦しんでいる人が少しずつ前を向いて生活が送れる手助けになれば幸いです。
①拒否
ペットが亡くなって1番最初にくる感情は「拒否・拒絶」です。
大事なペットが亡くなったことが信じられず「あの子はまだ生きている」「亡くなっていない」と現実を受け止められません。
そして、大きなショックにより放心状態になってしまい、なにも考えられなくなります。
②怒り
少しずつペットが亡くなった実感が湧いてきます。
ペットの死を誰かの責任にしたくて、怒りがこみ上げてくることもあります。
例えば、看取ってくれた病院の先生や家族、自分に怒りを感じてしまう場合もあるでしょう。
③交渉
怒りがおさまり「誰かを責めて怒っても仕方がない」と冷静に理解できるようになります。
そして「ペットにもう一度会いたい」「生き返らせてほしい」と神様などに交渉する段階にはいります。
④悲しみ、抑うつ
「どんなことをしてもペットが戻ってくることはない」と理解すると、涙が出たり深く落ち込んだりします。
この段階で、しっかりと泣き悲しむことで、次の段階に上手く切り替えられるようになります。
⑤受容、回復
たくさん泣いて悲しんだあとは、少しずつペットの死を受け入れられるようになります。
悲しい感情だけではなく、ペットとの楽しかった思い出も思い出せるようになるでしょう。
①~⑤の順番は人によってバラバラだったり、行ったり来たりしてしまう場合もあります。
立ち直るためには、悲しい時はたくさん泣いて、自分の感情に素直になることが大切です。
家族や周囲ができるペットロスの人への接し方

ペットロスに苦しんでいる人が、あなたに頼ってきた時「なんて言えばいいのだろう」と悩んでしまう人も多いでしょう。
以下では、ペットロスになった人への接し方について紹介していきます。
悲しい気持ちに寄り添ってあげる
身近な人がペットロスに苦しんでいる時は、そっと寄り添ってあげましょう。
相手の話をゆっくり聞き、一緒に思い出話をして、悲しい気持ちにたくさん共感してあげましょう。
悲しい気持ちでいっぱいの相手に、アドレスや意見を言うことは逆効果です。
必ず、肯定しながら「辛かったね」「一緒に過ごせて楽しかったね」などと声をかえてあげましょう。
ペットの死後の手続きや遺品整理を手伝う
ペットが亡くなると、お葬式・火葬などの手続き、遺品整理などをする必要があります。
しかし、悲しみでいっぱいの飼い主さんは放心状態になっており、なにも手につかなくなるでしょう。
そんな時、あなたが手伝ってあげることで、飼い主さんの負担も減らすことができます。
なにもできなくても受け入れてあげる
ペットが亡くなってからしばらくの間は、家事や仕事に集中できない日々が続くでしょう。
大事な家族とお別れするのは、本当に辛いことなので仕方ありません。
周囲の人もその状況を受け止めてあげ、回復するまで見守ってあげましょう。
また、ペットロスの人に向けた本も多く販売されているので、プレゼントしてみてはいかがでしょうか?
3つのペットロス対策

何度経験しても、ペットとのお別れは非常に辛く悲しいものです。
しかし、ペットロスに陥り、飼い主さんの精神状態や健康状態のバランスが崩れてしまうと日常生活に支障が出てしまいます。
あらかじめ重症化させないためにも、以下の3つを対策をしておきましょう。
①ペットを家族に迎え入れる前に覚悟をもつ
かわいい犬を目の前にすると「飼いたい」という気持ちでいっぱいになりますが、飼う前に以下の2つのことを頭に入れておきましょう。
飼う前の覚悟
- ペットは人間より寿命が短いので必ずお別れの日がくる
- その大事な命を何があっても最後まで看取る覚悟をもつ
ペットは寿命が短い分、成長スピードがはやいので介護をする時がくるかもしれません。
また、ペットが病気した時は動物病院に連れて行き、手術が必要なら高額な医療費が必要になります。
「可愛い」だけの軽い気持ちで飼うのではなく、最後まで看取る覚悟をもって家族に迎え入れましょう。
②日頃から体調管理を徹底する
定期的に健康診断を受けさせ、体調管理を徹底しましょう。
肥満気味の犬は、何らかの病気になりやすくなるので寿命を縮める原因になり兼ねません。
そのため、体重管理もしっかりと行いましょう。
日頃から体調管理をすることはペットにとっても良いことですし「あの時病院に連れて行けばよかった」などの飼い主さんの後悔も防げます。
犬のダイエット方法について詳しく紹介している記事はこちら
-

-
参考記事犬に効果的なダイエット方法とは?ダイエットのコツや注意点を紹介!
愛犬が幸せそうにご飯を食べている姿を見ていると、ついつい与えすぎてしまう飼い主さんも多いでしょう。 筆者も「少しだけなら大丈夫かな」と、ついつい愛犬におやつを与えてしまうことがあります・・・ しかし、 ...
続きを見る
③ペットの終活準備をしておく
ペットが亡くなると放心状態になっていることが多いので、正常な判断ができなくなるでしょう。
そのため、火葬やお葬式が終わってから「自宅の私有地に埋葬したかった」「違う業者に頼みたかった」など後悔する人も多いです。
ペットとのお別れの方法に後悔しないためにも、事前に以下のことを決めておくといいでしょう。
事前に決めておくべきこと
- どんな葬儀にするのか
- 火葬の時どのように見送りたいか
- 火葬後はどのように供養するのか
- どの業者に依頼するのか
- 火葬、供養の予算
- 火葬・供養のスケジュール
愛犬と過ごした日々をいい思い出に!

おさらい
- ペットとお別れした時はたくさん悲しんで思いっきり泣く
- 日頃からペットの健康管理を徹底する
- 飼う前に人間より寿命が短いということを頭に入れておく
大事なペットとのお別れは、言葉では言い表せないくらい悲しく辛い出来事です。
筆者もお別れした後の何ヵ月間は写真を見ることもできないくらい落ち込みました。
すぐに立ち直ることはできないですが、少しずつペットとの生活を楽しい思い出として受けとめましょう。
いつかは来るペットとのお別れは避けれないので「覚悟」をして飼いましょう。