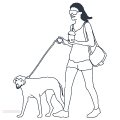「最近、愛猫の体付きが丸くなってきたな・・・」と愛猫の体型について、心配している方もいらっしゃるのではないでしょうか?
猫は太りやすい体質なのでフードを食べすぎてしまうと、あっという間に「肥満」になってしまいます。
しかし、飼い主さんによっては「少しぽっちゃりくらい」だと、愛猫の肥満に気づいていない方も少なくありません。
そこで、今回は「猫が肥満体型になる原因や肥満によって引き起こされる病気」「正しいダイエット方法」について紹介します。
この記事を参考に、愛猫の体重管理を徹底しましょう!
この記事を読んでわかるポイント
- 肥満の基準・瘦せすぎの基準がわかる
- 猫種ごとの適正体重がわかる
- 肥満になるが原因がわかる
- 肥満が原因で引き起こされる病気がわかる
- ダイエット方法(食事・運動)がわかる
【Contents】
肥満の基準と痩せすぎの基準

肥満体型といっても、基準が分からないという方も多いでしょう。
ここからは、肥満の基準と瘦せすぎの基準について紹介していきます。
以下のことを参考に、愛猫に照らし合わせて考えてみましょう。
猫の肥満の基準
まずは、猫の背骨や肋骨に触れてみて、骨が手に触れるようであれば肥満の心配はありません。
しかし、背骨や肋骨に触れられないほどの分厚い皮下脂肪が付いている場合には、肥満の可能性があります。
さらに、猫を上から見て腰のくびれが無い場合も、肥満になっている証拠です。
一方、猫のお腹がだるーんとなっているのは「ルーズスキン」とよばれるものなので、太っているわけではありません。
猫がのびのび自由に動くために必要なゆとりであり、腹部を守る役割もあります。
猫の瘦せすぎの基準
上から見た時に腰のくびれがとても細く、横から見るとお腹が吊り上がっている場合には「瘦せすぎ」の可能性が高いです。
多少の皮下脂肪や筋肉があれば「痩せている」状態ですが、皮下脂肪や筋肉が付いておらず骨と皮の状態であれば「瘦せすぎ」といえるでしょう。
瘦せすぎてしまうと、背骨がゴツゴツ突き出して被毛の艶も無くなります。
元気で体調などに異変がないのに、どんどん痩せてしまう場合には「甲状腺機能亢進症」や「慢性腎臓病」の可能性も考えられるため、早急に動物病院を受診しましょう。
猫種ごとの適正体重

猫種によって、適正体重が異なります。
ここからは、猫種ごとの適正体重の目安を紹介するので、愛猫が肥満かどうかを判断する参考にしてください。
| 猫種 | オス | メス |
| アビシニアン | 3.0㎏~5.㎏ | 3.0㎏~5㎏ |
| アメリカン・カール | 2.5㎏~4.5㎏ | 2.5㎏~3.5㎏ |
| アメリカン・ショートヘア | 3.0㎏~6.0㎏ | 3.0㎏~5.0㎏ |
| ベンガル | 3.0㎏~6.0㎏ | 3.0㎏~5.0㎏ |
| バーマン | 3.0㎏~6.5㎏ | 3.0㎏~5.0㎏ |
| ブリティッシュ・ショートヘア | 3.0㎏~5.5㎏ | 3.0㎏~5.0㎏ |
| シャルトリュー | 4.0㎏~6.5㎏ | 3.0㎏~5.0㎏ |
| エジプシャン・マウ | 3.0㎏~5.5㎏ | 3.0㎏~4.0㎏ |
| エキゾチック・ショートヘア | 3.0㎏~5.5㎏ | 3.0㎏~4.0㎏ |
| ジャパニーズ・ボブテイル | 3.0㎏~4.5㎏ | 3.0㎏~4.0㎏ |
| メイン・クーン | 3.5㎏~6.5㎏ | 3.0㎏~6.0㎏ |
| マンチカン | 3.0㎏~6.0㎏ | 3.0㎏~6.0㎏ |
| ノルウェージャン・フォレスト・キャット | 3.5㎏~6.5㎏ | 3.5㎏~5.5㎏ |
| オシキャット | 3.5㎏~6.5㎏ | 3.0㎏~5.5㎏ |
| ペルシャ | 3.0㎏~5.5㎏ | 3.0㎏~5.0㎏ |
| ヒマラヤン | 3.0㎏~5.5㎏ | 3.0㎏~5.0㎏ |
| ラガマフィン | 4.0㎏~7.0㎏ | 4.0㎏~6.0㎏ |
| ラグドール | 4.0㎏~7.0㎏ | 4.0㎏~6.0㎏ |
| ロシアンブルー | 3.0㎏~5.0㎏ | 3.0㎏~5.0㎏ |
| スコティッシュ・フォールド | 3.0㎏~6.0㎏ | 3.0㎏~5.0㎏ |
| セルカーク・レックス | 3.0㎏~6.5㎏ | 3.0㎏~5.0㎏ |
| シャム | 3.0㎏~4.0㎏ | 3.0㎏~4.0㎏ |
| オリエンタル・ショートヘア | 3.0㎏~4.0㎏ | 3.0㎏~4.0㎏ |
| サイベリアン・フォレスト・キャット | 4.0㎏~8.0㎏ | 4.0㎏~6.0㎏ |
| シンガプーラ | 2.0㎏~3.5㎏ | 2.0㎏~3.5㎏ |
| ソマリ | 3.0㎏~5.0㎏ | 3.0㎏~4.5㎏ |
| トンキニーズ | 3.0㎏~5.0㎏ | 3.0㎏~4.5㎏ |

肥満体型になる原因

猫が肥満になる原因は、人間が太る原因とほとんど同じです。
ここからは、猫が肥満になる原因について紹介していくので、当てはまる箇所が多い場合は改善するようにしましょう。
運動不足
運動するスペースが狭く走り回ることが難しいことから、室内飼いをしている猫は運動不足になりがちです。
猫はとても活発な動物なので、運動不足は肥満だけではなくストレスの原因にも繋がります。
そのため、運動量を増やすための改善策を考える必要があります。
フードの食べ過ぎ
可愛い顔でおねだりされると、ついついフードやおやつを与えすぎてしまう人も多いでしょう。
しかし、フードやおやつの与えすぎは、肥満の大きな原因になるので要注意です。
キャットフードに記載されている目安量を守り、愛猫に適した量を与えるようにしましょう!
去勢手術・避妊手術
去勢手術・避妊手術を行うと、ホルモンバランスが変化します。
そのため、食欲が増えたり、基礎代謝が低下する場合があります。
食欲増進や基礎代謝の低下を防ぐ方法はありませんが、去勢・避妊手術が終われば「去勢・避妊手術した猫用」のキャットフードに切り替えることをおすすめします。
病気・怪我
病気や怪我をすると運動量が減少するので、肥満になりやすくなるでしょう。
また、甲状腺機能低下症やクッシング症候群など、内分泌に異常が出ることで太りやすい体質になります。
加齢
人間と同じように、年齢を重ねるごとに基礎代謝が低下して太りやすくなります。
シニア期を迎えてからも、若い時期と同じフードではカロリーが高すぎる場合があるので、フードの見直しをしましょう。
体質
猫にも人間と同じように、太りやすい体質・太りにくい体質があります。
体質の改善は難しいので、現状の体重より体重が増えないように気を付けましょう。
肥満が原因で引き起こされる病気

体が小さな猫にとって肥満は大きな負担になるので、さまざまな病気の引き金になります。
肥満が原因によって引き起こされる病気は以下のとおりです。
肥満が原因で引き起こされる病気
- 関節・靭帯の疾患
- 心臓・呼吸器疾患
- 糖尿病
- 腫瘍
- 皮膚炎
- 尿路感染
- 肝リピドーシス(脂肪肝)
- 口腔内歯牙疾患
- 妊娠時の合併症
- 創傷治癒の遅れ
- 感染症リスクの増加
- 手術・麻酔リスク増加

ダイエット方法【食事編】

肥満になっている猫は、まず「食事改善」が必要です。
食事改善といっても、食事の量を減らせばいいということではありません。
以下で、食事改善について詳しく紹介していきます。
適量な量を計量して与える
今まで与えてきたフードの量で、猫が肥満になっている場合には、フードを与えすぎている可能性があります。
キャットフードには目安量が記載されていますが、年齢や体型、体質などによって適切な量は異なります。
そのため、愛猫に適したフードの量を知りたい方は以下の計算式に当てはめて考えてみましょう!
成猫に適したフードの量の計算式
猫の体重×70~80Kcal=必要Kcal
肥満猫に適したフードの量の計算式
理想の体重×35~40Kcal=必要Kcal

食事の回数を増やす
肥満の猫には、食事の回数を増やすとダイエット効果が期待できます。
食べたフードを消化し、それを吸収することにもエネルギーを使い、このことを「食餌性熱効果」いいます。
食事をこまめに分けて与えることで、消費するエネルギーが高くなりダイエットに繋がるのです。

早食いを防止する
肥満の猫は、食事の際に「早食い」をしがちです。
満腹中枢はすぐに働かないので、早食いをすると食べ終わっても「まだ食べたりない」と満足できません。
そのため、時間をかけてゆっくり食事を摂ることで、満足感を得られるようになります。
以下の商品のような、迷路型や突起のあるお皿を使用して、早食いを防止しましょう!
ダイエットフードを与える
猫が太っているからといって1番してはいけないのが「フードを極端に減らす」ことです。
急にフードを減らすことでストレスが溜まり、体調を崩しかねません。
そのため、減量したいと考えている場合には「ダイエットフード」に切り替えることをおすすめします。
ダイエットフードを選ぶ際には、猫に必要な栄養素である「タンパク質」が多く含まれているかチェックしてください。
最近のキャットフードには、タンパク質に加えてビタミンやミネラルなども豊富に含まれています。
さらに、適度な食物繊維が含まれているキャットフードを選ぶことで、肥満の猫も満足感を得ることができるでしょう。
ダイエット方法【運動編】

肥満を改善するためには、食事管理だけではなく「適度な運動」も大切です。
以下のような商品を揃えて、室内でも運動ができる環境を整えてあげましょう!
キャットタワーで運動させる
室内で飼育している猫にダイエットさせたい場合には「キャットタワー」を設置するといいでしょう。
キャットタワーは種類が豊富で、おもちゃや爪とぎ、寝るスペースなどが付いているものもあります。
また、高低差のある運動をするとストレス解消にもなるといわれています。
なかなか愛猫がキャットタワーに登らない場合には、キャットタワーの上におやつを置く・キャットタワーの上で猫じゃらしを使用するなどすると、徐々に慣れてくるでしょう。
おもちゃを使って運動させる
飼い主さんがおもちゃを使って運動させることで、肥満な猫のダイエットに繋がります。
以下では、ダイエットに最適なおもちゃを紹介していくので、ぜひ参考にしてください♪
猫じゃらし
猫の代表的なおもちゃ「猫じゃらし」は、ダイエットに最適のアイテムです。
釣り竿のようになっており、先端に羽やボールが付いているので、猫の野生本能をくすぐります。
猫の様子を見ながら調節できるので、無理せずに運動させることができます。
追いかけるおもちゃ
飼い主さんが動かさなくても、自動的に羽やネズミのおもちゃが動いてくれます。
おもちゃは予測不可能な動きをするので、猫も夢中になること間違いなし!
リモコンで飼い主さんが操作して動かせるものもあるので、猫も飽きずに遊べるでしょう。
トンネル系のおもちゃ
猫は薄暗く狭い場所が好きなので、トンネル系のおもちゃを気に入ってくれるでしょう。
しかし、トンネルが細すぎると肥満の猫は通れない可能性があるので、購入前にサイズを確認してください。
爪とぎが付いているものや、おもちゃが付いているものもあるので、愛猫が気に入りそうなトンネル系のおもちゃを選びましょう。
肥満の猫が注意すべきポイント

ここからは、肥満の猫が気を付けるべきポイントについて紹介していきます。
愛猫が健康に長生きできるように、飼い主さんが食事や快適な生活のサポートしてあげましょう。
不衛生にならないように気を付ける
猫は肥満になると、体を丸めて毛づくろいすることが難しくなります。
そのため、自分で体を清潔に保てなくなるので、皮膚病にかかるリスクが高くなります。
そのような状況を避けるためにも、飼い主さんが水で濡らしたタオルやペット専用のボディシートで拭いてあげましょう。
愛猫が排泄した後は、足裏や陰部などを確認して不衛生にならないよう気をつけてあげてください。
高い場所からジャンプさせない
肥満の猫には、高い場所からのジャンプや階段の上り下りはさせないようにしましょう。
着地の衝撃によって、背骨や椎間板、四肢の関節にダメージを与え、脱臼や骨折、靭帯を損傷する危険性があります。
そのため、猫が高い場所に行きたがっている場合には、踏み台やスロープを設置するなどして、体に負担を与えないようにしましょう。
無理のない程度でダイエットをしよう

おさらい
- 肥満になると病気のリスクが高くなる
- 肥満の猫には高い所からのジャンプや階段の上り下りをさせない
- ダイエットさせるためには食事管理・適度な運動が効果的
猫にとって「肥満」は、体に大きな負担を与え健康に悪影響を及ぼします。
大事な愛猫に長生きしてもらうためには、体重管理を徹底する必要があります。
この記事を参考に、肥満体型の猫はダイエットして、健康的な生活をサポートしましょう!