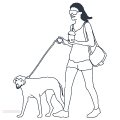犬にとって大好きな散歩なはずなのに「急に足を止めて歩かなくなった」という経験したことがある飼い主さんも多いでしょう。
そんな時、犬のリードを引っ張って、無理矢理歩かそうとしたことはありませんか?
実は、その行動は「絶対にしてはいけない対処法」の1つで、根本的な解決にはなっていません。
そこで、今回は「犬が歩かなくなる原因と対処法」「絶対にしてはいけないしつけ方法」を紹介していきます。
この記事を参考に、犬が散歩中に歩かなくなる原因を特定し、それに合った対処法を見つけましょう!
この記事を読んでわかるポイント
- 散歩に行くことで得られるメリットがわかり
- 犬が散歩中に歩かなくなる原因と対処法がわかる
- 犬が歩かなくなった時に「絶対にしてはいけないしつけ方法」がわかる
【Contents】
散歩をすることで得られる「メリット」

犬を飼っている方は、毎日の習慣の1つとして「散歩」に行っている方が多いでしょう。
しかし、犬にとって「散歩」はなぜ必要なのでしょうか?
ここからは「散歩をすることで得られるメリット」を紹介していきます。
散歩をすることで得られるメリットは以下のとおりです。
3つのメリット
- 運動不足が解消される
- 社会性を身につけられる
- 飼い主さんとのコミュニケーションを深めることができる
1.運動不足が解消される
近年、室内で飼育されている犬が増えているので、家で過ごす時間が増えています。
そのため、運動を十分にできず運動不足になってしまい、ストレスが溜まっている可能性があります。
そんな時に「散歩」をすることで、運動不足が解消されるので「肥満防止」の効果も期待できるでしょう。
また、溜まったエネルギーを発散することもでき、ストレス解消にも繋がります。
2.社会性が身につけられる
室内で飼育されている犬は、常に同じ景色や環境で生活しています。
そんな状況に長期間いると「見慣れない景色や乗り物・人物」を、外で見た時に刺激が強すぎて、恐怖心や不安感を抑えることができなくなります。
しかし、子犬の頃から散歩に行くことで「乗り物・他の犬・人物」など、さまざまな外の環境に触れさせることができます。
さらに、犬が散歩中に匂いや音を感じることで、外の環境に慣れることができ、少しずつ社会性が身に付きます。
上記のことから「散歩」は、犬の社会性を身につけるために「有効的」だといえるでしょう。
3.飼い主さんとのコミュニケーションを深めることができる
「散歩」には、犬と飼い主さんのコミュニケーションを深める大事な役割があります。
散歩中にコミュニケーションをとり、アイコンタクトをとる習慣をつけることで「問題行動」を防ぐことができます。
また、毎日散歩することで、犬の怪我・体調の変化に気づくことができ「早期発見」に繋がるでしょう。
室内で飼育していると見落としやすい変化も、散歩中に気づけることがあるので、犬と飼い主さんの信頼関係を深めるためにも「散歩」はとても大切です!
【犬種別】適切な散歩の頻度と時間

犬の散歩は1日何回行き、どのくらいの時間歩いていますか?
犬の体の大きさや年齢によって、適切な散歩の頻度・時間は異なります。
ここからは、小型犬・中型犬・大型犬それぞれに合った「適切な散歩の頻度・時間」を紹介していくので、愛犬に当てはめて考えてみましょう!
小型犬
小型犬の散歩は「1日1回30分程度」が適正だとされています。
小型犬の中でも、超小型犬といわれている「チワワ」は、他の犬と比べて骨が細いので、長時間の散歩は体に大きな負担を与えてしまうので注意が必要です。
反対に、小型犬の中に分類される「ジャックラッセルテリア」と「ミニチュアシュナウザー」は、他の小型犬より多くの運動量を必要とします。
そのため、小型犬の中でも犬種に合わせて、散歩時間・頻度を変えていきましょう。
小型犬
トイプードル・ミニチュアダックスフンド・パグ・ミニチュアシュナウザー・ジャックラッセルテリア etc...
中型犬
中型犬の散歩は「1日2回、1回あたり約30分~40分」の散歩が適正だとされています。
小型犬とは運動量が大きく違うので、歩くだけの散歩では満足できずエネルギーが発散できません。
そのため、たまには誰もいない場所で思いっきり遊ばせてあげることも大切です。
中型犬
柴犬・コーギー・ブルドッグ・コーギー・ビーグル・ボストンテリア etc...
大型犬
大型犬の散歩は「1日2回、1回あたり約60分」の散歩が適正だといわれています。
大型犬は小型犬や中型犬と体の大きさが違うので、過度な運動をしてしまうと、足に大きな負担がかかってしまいます。
そのため、中型犬の運動量の多い「走る」散歩ではなく、ゆっくりと時間をかけて「長く歩く」散歩を心掛けましょう♪
大型犬
ラブラドールレトリバー・ゴールデンレトリーバー・ダルメシアン・ドーベルマン etc...
不安感・トラウマなどの心理的な原因

犬にとって大好きな散歩なはずなのに、急に足を踏ん張って立ち止まってしまうことがあります。
散歩に行くまでは元気で、いつもと変わりはないのになぜだろう?と疑問に感じてしまう飼い主さんも多いでしょう。
身体に異常がないのに歩かなくなる時には「恐怖・不安・トラウマ」などの心理的なものが原因の可能性があります。
そこで、ここからは「心理的原因によって犬が歩かなくなる理由」と、その対処法について紹介します。
恐怖や不安を抱いている
「交通量が多い場所・大きな音が聞こえる場所・はじめて通る散歩ルート」などで立ち止まってしまう場合は、恐怖や不安を感じて、警戒している可能性が高いでしょう。
「大きな音・見知らぬ人・他の犬・乗り物が通る」などの突発的な刺激は、犬は警戒し恐怖のあまり足がすくんでしまいます。
とくに、社会性を身につけていない犬・子犬・音や振動に敏感な犬は、恐怖心から立ち止まってしまうことが多くあるでしょう。
飼い主さんの後ろに隠れようとする・耳を伏せる・尻尾を下げている場合には、犬が怖がっている証拠です。
対処法
おやつやおもちゃなど犬が好きなものを見せながら歩きましょう!
その場所から少し離れることができれば、散歩を再開してくれる場合があります
トラウマを思い出した
以前、散歩している最中に「大きな犬に吠えられた」「知らない人に急に撫でられた」などの、トラウマになるような経験をしている犬は、散歩中に立ち止まってしまうことが多い傾向にあります。
散歩中にトラウマになっている出来事と同じような状況に出くわしてしまうと、嫌な記憶がよみがえり歩けなくなってしまうのです。
このような場合には「口付近を舐める・後ろ足を使って身体を掻く・あくびを繰り返す、地面の匂いを嗅ぐ・掘る」という行動がみられます。
対処法
愛犬が好きな物を見せて誘導してみる
散歩ルートを変更してみる
自己主張が強い
散歩をしている時に、飼い主さんと犬が行きたい方向が食い違った時、犬は歩くのをやめて立ち止まることで「行きたくない」とアピールしています。
このような時は、飼い主さんが行きたい方向とは逆の方を向いて、飼い主さんの呼びかけにも反応しないことも多いでしょう。
対処法
飼い主さんが犬と一緒に立ち止まってしまうと、犬は自分の意見が通ったと思い、さらに自己主張が強くなる可能性があります。
そのような場合には飼い主さんが犬に声をかけ、号令に従ったら「ご褒美」を与えて、飼い主さんについてきてくれるようにしつけましょう。
散歩グッズに慣れていない
子犬が散歩デビューする時に、初めてリードやハーネスをつけると慣れない感覚に戸惑って、歩かない場合があります。
また、成犬であっても新しい「リード・ハーネス・靴・レインコート」を着せた時に違和感を感じて、立ち止まってしまうことも・・・
対処法
新しいグッズは散歩に行く前に、まずは家で使用して慣れさせましょう!
その時に、飼い主さんが不安そうに見ていると、犬も飼い主さんの気持ちを感じ取って不安になってしまうので、大げさに褒めてあげることがポイントです
愛犬にピッタリなハーネスやリードの「散歩グッズ」を知りたいという方は、以下の記事を参考にしてください♪
-

-
参考人気犬用リード8選を徹底比較!利用者の口コミや特徴も詳しく紹介
愛犬の散歩に必要なアイテム「犬用リード」 犬用リードには「機能性」「デザイン性」などに、特化したたくさんの種類があるので、選ぶのに迷ってしまう飼い主さんも多いのではないでしょうか? そこで今回は、犬用 ...
続きを見る
怪我や病気による身体的な原因

ここからは「身体的原因によって犬が歩かなくなる理由」と、その対処法について紹介していきます。
怪我や病気などが原因で立ち止まっているのなら、無理に歩かせずに抱きかかえて連れて帰りましょう。
疲労が溜まって動けない
いつもより長い距離を歩いたり、たくさん走り回って遊んでいると、疲労が溜まって動けなくなります。
動き好きで疲れている時は体温が上昇するので、舌を出しながら「ハァハァ」と荒い息遣いをしているでしょう。
対処法
犬が疲れている場合には涼しい場所で少し休憩して水分補給をすると回復することが多いです
また、体温が上昇している場合には冷水をかけたり鼠径部を保冷剤などで冷やすと体温が下がります
怪我をして痛みがある
犬が散歩中に足を引きずっていたり、歩き方に異変がある時は「怪我」をしている可能性が高いでしょう。
まずは外傷がないか「肉球・爪の間・足」を確認して、足を引っ込めるような素振りをしたら、その周辺に痛みがあるサインです。
また、スキップするような歩き方・腰をクネクネする歩き方などをしていたら、以下の疾患が考えられます。
関節炎・股関節異形成・椎間板ヘルニア・変形性脊椎症・骨折
上記のどれかに当てはまる時は強い痛みがあるので、足を触ろうとすると噛んだり歯を剥き出しにして威嚇してきます。
このような場合には、症状が悪化しないうちに、早急に病院を受診しましょう!
対処法
足を痛そうに引きずっている場合には、早急に病院を受診してください。
病院に連れていく時は、バスタオルや板に乗せて安全に連れていきましょう。
何らかの病気になって体が動きずらい
散歩を始めてすぐに「ハァハァ」と息遣いが荒くなっている場合には「呼吸系・心臓」に疾患がある可能性があります。
運動不足の犬・肥満気味の犬も息遣いが荒くなりますが、肥満が原因で肝臓の病気になっている場合もあるので注意が必要です。
対処法
すぐに息切れしている・呼吸が苦しそうな場合には早急に病院を受診しましょう
熱中症になっている
夏の暑い時期に散歩に行くと、体温が上昇して「熱中症」になってしまい、動かなくなってしまいます。
また、アスファルトが暑すぎて肉球が地面につけれず、立ち止まっている可能性もあるでしょう。
対処法
お腹周り・鼠径部を触っていつもより体温が熱い場合には、すぐに冷やしてあげましょう
回復がみられない時には、早急に病院を受診してください
【年齢別】考えられる散歩中に歩かない原因

犬が成長段階によって、さまざまな原因によって歩かなくなる場合があります。
そこで、ここからは「成長段階別で考えられる歩かない原因」について紹介します。
子犬
子犬が散歩中に歩かなくなる理由として、考えられる原因は以下のとおりです。
抱っこして散歩することに慣れた
子犬の散歩デビューは、抱っこした状態やカートに乗せて外に慣れさせることから始めた方が多いでしょう。
しかし、それが習慣になってしまうと歩くことが嫌になってしまい、立ち止まって抱っこを要求するようになります。
まだ帰りたくない
少しずつ身体も成長して今まで以上の運動量が必要になると、いつもの散歩コースでは満足できなくなります。
そのため、散歩コースの折り返し地点から、立ち止まり始めて「まだ帰りたくない」とアピールします。
恐怖心があり動けない
生後16週目までは「社会化期」なので、好奇心旺盛で怖いもの知らずですが、社会化期が終わると「恐怖心」が芽生え始めます。
そのため「他の犬・初めて会う人・初めての散歩コース」など、不意に起こる出来事に警戒心を持ち、身の安全を守るために立ち止まってしまいます。
肉球が温度に敏感に反応するので歩けない
子犬の肉球は「ぷにぷに」しているので、熱い温度も冷たい温度も感じやすくなっています。
そのため、夏のアスファルトが熱くなる時期や、反対に冬の冷たくなる時期には、地面に肉球をつけることを嫌がります。
対処法
散歩に慣れてきたら少しずつ距離を伸ばしていきましょう
また、散歩は気温に合わせた時間帯を考えて、犬が快適に散歩できる時間に行ってください
成犬【生後6ヶ月~2歳】
成長期の犬は筋骨格系が成長の途中段階なので「ジャンプのしすぎ・走りすぎ・硬い地面を歩きすぎる」と、足に負担がかかります。
そのため、関節に痛みを感じてしまうので、立ち止まって歩かなくなってしまいます。
対処法
激しい運動をした後の散歩は控えたほうがいいでしょう。
シニア犬【9歳以上】
犬は9歳を過ぎると「シニア期」に突入するので、筋力が衰えはじめ、体力が無くなってきます。
今までは、何ともなかった散歩の距離も、シニア期になると途中で疲れて止まってしまうことが増えます。
また、体力の低下と共に「夜泣き・粗相」という症状がみられる場合には、他の病気を疑った方がいいでしょう。
対処法
シニア犬にとっても「散歩」はストレス解消・健康維持にとても大事な役割をもっています
しかし、足腰に負担がかからないように、筋肉をほぐしたりケアをすることが大切です
犬が散歩中に歩かない時の5つ対処法

犬が散歩の途中で歩かなくなってしまった時は、歩かない原因を明確にして、その対処法を考える必要があります。
以下のことを参考に、愛犬が快適に散歩に行けるように工夫してあげましょう!
5つの対処法
- 抱っこしてあげる
- いつもの散歩ルートを変えてみる
- いつもの散歩の時間を変えてみる
- 散歩の時間を少し減らしてみる
- ご褒美のおやつを用意する
抱っこしてあげる
散歩の途中に歩かなくなる原因が「恐怖や不安」などの心理的なものなら、一時的に抱っこする対処法は有効的です。
恐怖を感じたまま散歩を続けると「トラウマ」になりかねません。
そのため、恐怖心を和らげてあげるためにも、抱っこして安心させてあげましょう!
いつもの散歩ルートを変えてみる
いつもの散歩のルートに「相性が合わない犬がいる」「音がうるさい場所がある」という場合には、思い切ってルートを変更してみましょう。
そうすることにより、犬の気分転換になるので、立ち止まらずに歩いてくれる場合があります。
いつもの散歩の時間を変えてみる
散歩の時間帯を変更することで「車の多さ・人通り」などが変わります。
そのため「車の多さ・人通り」などに恐怖心を感じている場合には、時間帯を変更することで犬にとって「嫌なこと」を排除できる可能性があります。
散歩の時間を少し減らしてみる
「散歩の時間が長い・距離が長いこと」により、犬が疲れて歩かなくなっている場合には、散歩時間を見直すことをおすすめします。
適切な散歩の「距離・時間・回数」は、犬種によって異なり、さらに年を重ねることに変化していきます。
そのため、犬が散歩の途中で疲れているようなら、散歩の時間などを見直す時期なのでしょう。
ご褒美のおやつを用意する
根本的な解決策にはなりませんが「おやつ」は一時的な気分転換にとても役立ちます。
犬が散歩の途中で歩かなくなった時には、ひとまずおやつを与えて、その日の散歩を終わらせましょう。
そして、次の日から「散歩ルート・散歩時間」などを変更して、犬の気分を変えることおすすめします♪
犬が歩かなくなった時に「絶対にしてはいけない」しつけ方法

犬がなかなか歩いてくれないと、飼い主さんも焦ってイライラしてしまうこともあるでしょう。
しかし、犬が歩かないからといって、間違えたしつけを行うと逆効果になってしまう可能性が高いです。
そこで、ここでは「絶対に行ってはいけないしつけ方法」について紹介していきます。
大きな声で怒る
犬が立ち止まってしまうのには、必ず何かしらの原因があります。
その原因を無視して犬を大きな声で怒ってしまうと、飼い主さんとの信頼関係を壊したり、怒られた場所がトラウマになってしまうでしょう。
そのため、散歩中に犬が足を止めてしまった時には、大きな声で怒るのではなく「歩かない原因を探す」ことが大切です!
リードを引っ張って無理矢理歩かせる
散歩中に犬が歩かなくなった時に、グっと進行方向にリードを引っ張ったことはありませんか?
これはよく見かける光景ですが、実は1番行ってはいけないしつけ方法です。
引きずられることで、犬は「恐怖・怒り」を感じ、余計に歩くことが嫌になってしまいます。
さらに、肉球を摩擦で擦りむいてしまったり、首を痛めてしまう場合もあるでしょう。
リードを引っ張って歩かせることは、根本的な解決にならず怪我に繋がる可能性もあるので、絶対にやってはいけません。
ずっと抱っこする
散歩中に犬が歩かないからといって、ずっと抱っこすることはよくありません。
抱っこして散歩することに慣れてしまうと「抱っこの方が楽」「高いところからの景色が楽しい」と感じ、余計に歩くことが嫌になってしまいます。
そのため「抱っこしてほしいから歩かない」という状況になる可能性もあるので、ずっと抱っこして散歩することは避けましょう。
犬の行きたい方向に従い続ける
「この道は行きたくない」「まだ帰りたくないから違うルートに行きたい」という犬の意思に任せて散歩ルートを決めていると、自分がリーダーだと勘違いしてしまいます。
そのため、こっちの道に行きたいと立ち止まった時には、毅然とした態度で「NO」といえる飼い主さんになりましょう!
愛犬と散歩の時間を楽しもう!

おさらい
- 愛犬に適した散歩の「時間・回数・距離」を理解する
- 犬が歩かなくなった時は、リードを無理矢理引っ張らずに気分転換させる
- 散歩中に「休憩・安静」にしても、歩かないようなら「怪我・病気」の可能性があるので病院を受診する
散歩は、犬と飼い主さんの関係を深める大事な時間。
そのため、お互いにとって「散歩」の時間が楽しいと思えるように、快適な散歩方法を考えることが大切です。
万が一、散歩中に犬が歩かなくなってしまっても、その原因を考えて一緒に改善していく必要があります。
そんな時はこの記事を参考にすることで解決策が見つかるはずです♪