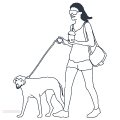飼っている愛猫が急に嘔吐してしまうと、ビックリしてあたふたしてしまう飼い主さんも多いでしょう。
猫が嘔吐する原因には、さまざまな理由があり、処置が遅れると死に至るケースも考えられます。
そのような状況を避けるためにも「嘔吐の原因・処置方法・予防策」を理解しておくことが大切です。
そこで、今回は「猫の嘔吐」について徹底解説していくので、猫を飼っている方は参考にしてください♪
この記事を読んでわかるポイント
- 猫が嘔吐する原因がわかる
- 急いで動物病院を受診するべきケースがわかる
- 嘔吐の頻度を減らす予防策がわかる
【Contents】
猫は頻繁に嘔吐する動物

家で飼っている猫が苦しそうな声を出しながら、嘔吐している姿を見ると非常に心配になります。
猫は他の動物に比べて、よく嘔吐する動物だといわれていますが、ここからはその理由について詳しく紹介していきます。
猫が狩りをしていた頃の習性
猫が頻繫に嘔吐する原因として考えられているのは「猫の習性」だといわれています。
元々猫は狩りをして獲物を捕まえており、その獲物を丸呑みの状態で胃の中に入れていました。
しかし、獲物の中には猫の胃袋よりも大きなサイズもあり、それを「消化しきれず外に吐き出す」ということを繰り返していたようです。
そのため、今現在も、狩りをしていた頃に行っていた「不快なものは嘔吐して外に出す」という習性の名残があるので、嘔吐を頻繁にしてしまうのでしょう。
猫の体のつくり
もう1つの猫が頻繫に嘔吐する理由は「猫の体のつくり」が関係しているといわれています。
猫がもっている高い運動能力を発揮するには、体が軽くなくてはいけません。
そのため、猫の「胃」は他の動物に比べて小さく作られており、胃の中に入る内容量も少なくなっています。
猫は胃の内容量が少ないのに、それ以上のフードを食べてしまうことが多いので、嘔吐を繰り返してしまうのでしょう。
また、猫の体は消化管が口から胃まで平衡に配置されているので、労力を使わずに嘔吐することができます。
そのため、猫は他の動物よりも、毛玉など消化できないような物・便で排出できない物を嘔吐することが得意なようです。
猫が嘔吐する原因

頻繁に嘔吐をする猫ですが、原因もなく嘔吐を繰り返しているわけではありません。
そこで、ここからは「猫が嘔吐する主な6つ原因」について紹介していきます!
6つの原因
- 食べすぎ・早食い
- 胃に毛玉が溜まっている
- 誤飲・誤食
- ストレス
- フードが体質に合っていない
- 空腹
食べすぎ・早食い
フードを食べすぎたり早食いすることで、フードが一気に胃の中に入るので、胃が対応しきれず嘔吐してしまいます。
また、前述したように、猫は狩りしていた頃に獲物を丸呑みしていたので、今もフードを丸呑みする名残があります。
そのため、フードが食道に詰まったり、消化不良を引き起こすと嘔吐してしまうのでしょう。
胃に毛玉が溜まっている
猫の舌にはトゲがあり、ブラシのような構造をしています。
そのため、猫がグルーミング(毛づくろい)を行うことで、舌に被毛が絡まり、そのまま体内に取り込んでしまうようです。
体内に入った被毛は、便と一緒に排出されることが多いですが、外に排出されず胃の中に溜まり続けている被毛もあります。
胃の中に大量に被毛が溜まると、猫は不快に感じるので、被毛を吐き出そうとするのでしょう。
嘔吐する頻度が高い猫種・時期
長毛種の猫は体内に入る被毛の量が多いので、嘔吐する回数が短毛種より多い
初夏や秋頃は猫の換毛期なので、被毛が抜けやすくなり胃に溜まりやすくなるため嘔吐する回数が増える
誤飲・誤食
輪ゴム・ビニール袋・おもちゃなど、猫が消化できない物を「誤飲・誤食」すると、異物を体外に排出しようとして嘔吐する場合があります。
また、リボン・ヒモなどは「蛇や小動物の小腸」のシルエットに似ているため、猫が誤食しやすいといわれています。
猫が誤飲・誤食しやすいような物は、保管方法に気を付けましょう!
ストレス
猫は「ストレス」を感じやすく、ストレスが体調に表れやすい動物です。
強いストレスを感じてしまうと「食欲不振」「嘔吐」「元気がなくなる」などの症状がおこります。
猫がストレスを感じる主な原因として、考えられるものは以下のとおりです。
ストレスの原因
引っ越し・環境の変化・新しいペットとの同居・運動不足・愛情不足
フードが体質に合っていない
猫のフードは、数え切れないほど多くの種類が販売されており、種類によって「粒の大きさ・硬さ・成分」などが異なります。
そのため、数多くの中から飼っている猫の「体質・好み」に合ったフードを選ぶことが大切です。
「このメーカー・原材料が含まれているフードは嘔吐しやすい」という場合は、フードが猫の体質に合っていないのでしょう。
そのような場合には、フードを他の種類に切り替え、猫の様子を確認してください。
空腹
食事と食事の間隔が長すぎて空腹状態が続くことにより、胃の中から「胃酸や胆汁」が出てきます。
胃酸や胆汁が出ると胃腸に負担をかけ、気分が悪くなり嘔吐に繋がってしまうようです。
また、空腹状態の空っぽの胃に、急にフードが入ってくると胃が対応しきれずに嘔吐してしまう場合もあります。
猫が嘔吐する原因として考えられる病気

上記で紹介した「猫が嘔吐する6つの原因」に当てはまらなかった場合「病気」の可能性を疑った方がいいでしょう。
頻繁に「嘔吐」を繰り返す場合に、考えられる病気は以下のとおりです。
嘔吐を繰り返している時に考えられる病気
- 毛玉症
- 胃炎・食道炎
- 慢性腎不全
- 甲状腺機能亢進症
- 腫瘍
- すい炎
- 汗腺性腸疾患
- 腸閉塞
毛球症
体内に入り込んだ猫の被毛がうまく排出されずに、胃の中で大きな毛玉になり、消化管につまってしまう病気です。
「毛玉症」の症状の程度は、胃の中に溜まっている被毛の量によって異なりますが、以下のような症状がみられることがあります。
また、可能性は低いですが、毛玉が胃から腸に入り込んでしまい、腸が壊死することで起こる「腸閉塞」になるケースもあります。
腸閉塞になった場合には、開腹手術をして体内にある毛玉を取り出さなければなりません。
症状
食欲不振・嘔吐・消化機能の低下
胃炎・食道炎
感染症やアレルギーなどが原因になり、胃や食道に炎症を起こしてしまう病気です。
また、生理的に嘔吐を繰り返した場合にも「胃炎・食道炎」を発症をすることが多い傾向にあります。
症状
食欲不振・嘔吐
慢性腎不全
血液中にある老廃物をろ過させて、尿として排出させる役割がある「腎臓」の機能が低下する病気を「慢性腎不全」といいます。
腎臓の機能が低下することで血液中の老廃物が多くなり、全身に毒素が回ってしまう「尿毒症」を引き起こす可能性があります。
症状
食欲不振・嘔吐・病状が進行すると死に至るケースもある
甲状腺機能亢進症
甲状腺機能亢進症とは、猫の喉付近にある「甲状腺」からホルモンが過剰に分泌されることで引き起こされる病気です。
心拍数が速くなる病気なので「心臓病」を併発してしまう可能性もあります。
症状
多飲多尿・体重が減少する・嘔吐・下痢
腫瘍
消化管やリンパ腺に「腫瘍」ができると、消化管が塞がれるので「嘔吐」する場合があります。
腫瘍ができる箇所や進行度合いによって、引き起こされる症状が異なります。
症状
重度の便秘・嘔吐
すい炎
近年、増加傾向にある膵臓に炎症が起こる病気を「すい炎」といいます。
膵炎になると、肝炎や糖尿病を引き起こす可能性もあるので注意が必要です。
症状
食欲低下・嘔吐・下痢
猫が嘔吐した内容物や色を確認しよう

猫が急に嘔吐してしまうとビックリして慌ててしまう飼い主さんが多いですが、猫の嘔吐の原因を明確にするためには「嘔吐の内容物」をよく観察する必要があります。
嘔吐物を処理してしまう前に「嘔吐物の色・内容物」を確認するようにしましょう!
毛玉を吐いた
前述したように、猫は頻繁にグルーミングするので、胃の中に被毛が溜まってしまいます。
胃の中に被毛が溜まりやすい猫・溜まりにくい猫は個体差によって異ります
嘔吐物の中身が毛玉だけなら、必要以上に心配する必要はありません。
黄色い液体
空腹状態の時や胃の機能が低下すると、透明な液体や黄色い液体を吐き出すことがあります。
この黄色い液体は「胆汁」といい、本来は「腸」に流れ込む成分です。
しかし、空腹状態が続いて胃の機能が低下すると、腸に流れ込むはずの胆汁が胃に逆流する場合があります。
上記のような理由で、胆汁が胃に逆流することにより、胃に負担がかかり「嘔吐」に繋がるのでしょう。
胆汁が逆流してこないようにする改善策は「空腹状態の時間を減らすこと」です。
少量の食事をこまめに与えて、空腹の時間を少しでも減らしましょう!
透明な液体や白い泡
猫が嘔吐した透明な液体や白い泡は「胃液」です。
上記で紹介した空腹時に嘔吐する「胆汁」と同じように、お腹が減りすぎると「胃液」を吐く場合があります。
食事を食べた後に、いつも通りの元気な様子に戻れば必要以上に心配することはありませんが、嘔吐を繰り返しているようなら病気の可能性を疑った方がいいでしょう。
また、異物を誤飲している場合に、なんとか胃の中から出そうとして胃液を吐いている場合もあります。
猫がいつもと違う様子なら、獣医師さんに相談してみましょう!
嘔吐物に血が混じっている
嘔吐物に血が混じっている場合には、まず血の色が何色かを確認しましょう!
ピンク色の吐血・・・口腔内出血/咽頭部の出血/食道内出血
(鼻からも同じピンク色のような血が出てきた場合は「心臓性肺水腫」の可能性も)
赤色の鮮血・・・胃/腸/肺
赤黒い吐血・・・消化器官内にある腫瘍の破裂・臓性肺水腫・胃がん
(出血してから嘔吐するまでに時間が経過しているので、血が黒っぽくなっている)
上記のように、嘔吐物の吐血の色によって、どこから出血した血なのかが分かります。
嘔吐物に異物が混じっている
嘔吐物に、ヒモ・輪ゴム・ビニール袋など異物が入っていた場合には、猫が誤飲したと考えられます。
嘔吐したあとに猫が元気そうに見えても、胃や腸の中にまだ残っている可能性もあり、消化しきれず消化不良を引き起こしてしまう可能性があります。
嘔吐物の異物を確認し、動物病院で胃や腸の中を確かめてもらいましょう!
緑色の液体や泡
緑色の液体や泡は、膵臓の炎症・胆汁が多量に分泌された時に出る成分です。
猫が異物を誤飲してしまった時に、その異物を早急に消化させるために、胆汁が多量に分泌すると考えられています。
また、誤飲した異物が腸につまってしまい腸閉塞になった場合や、頻繁に嘔吐を繰り返している時などにも、緑色の液体や泡を嘔吐することがあります。
腸閉塞になってしまった場合には、短時間で死に至るケースもあるので、早急に動物病院を受診しましょう。
消化されていないフード
フードを早食いしたり食べすぎてしまうと、胃にたどり着くまでに吐き出してしまったり、胃が消化しきれずにそのまま嘔吐してしまう場合があります。
嘔吐物に入っているフードの消化状況を確認することで、どの器官で異常が起きているのかが分かります。
例えば、半分消化されている状態なら「胃」ほぼ消化されている状態なら「十二指腸」や「腸」に異常があります。
ゆっくり時間をかけて食べているのに消化途中で嘔吐してしまう場合には、消化機能が低下しているのでしょう。
寄生虫
嘔吐物の中に動いているものが入っている場合は「寄生虫」の可能性が高いです。
寄生虫は便と一緒に排出されることも多いので、便も確認するようにしましょう。
寄生虫を発見したら写真や動画におさめて、獣医師さんに見せるとスムーズに診察ができます。
万が一、多頭外の場合には、他のペットにも付着している可能性があるので駆虫しましょう!
猫が嘔吐する前によくする行動と、そのあとの対処法

猫を飼っている方は、猫が嘔吐する前に「ウ”ェウ”ェ」と苦しそうな声を出しながら、えずいている場面を目にしたことはありませんか?
猫が嘔吐する前によく行う行動を理解して、的確な判断・処置を行えるようにしましょう。
猫が嘔吐する前によくする行動
猫が嘔吐する前によくする行動は以下のとおりです。
猫が嘔吐する前によくする行動
- 頭を下げる
- よだれが垂れる
- 元気がなくなる
- 小刻みに震えている
- 狭い場所や暗い場所に隠れている
- 横隔膜が収縮している
- 口を開きながら舌を出そうとしている
- 咳を頻繁にしている
上記のような行動がみられたら「吐く前・吐いた時・吐いた後」の様子を観察しましょう。
上記の3つの様子を確認することで、動物病院で診察を受ける時にスムーズに行えます。
猫が嘔吐したあとの対処法
猫が嘔吐した直後は、水やフードを与えないようにしましょう。
胃や腸、体のどこかに異変が起きている時に水やフードを与えると、胃腸運動が再び始まり状態が悪化してしまう可能性があります。
猫が嘔吐したあとに、体調が回復しないようであれば、動物病院を受診しましょう!
急いで動物病院を受診するべきケース

猫が急に嘔吐した場合、パニックになってしまい「病院に連れて行った方がいい?」「嘔吐物に血が混じっている時はどうすればいい?」とあたふたしてしまう飼い主さんも多いでしょう。
そんな時に、以下のチェックリストに猫の症状を当てはめてみて、1つでも当てはまるようなら早急に動物病院を受診することをおすすめします。
また、診察をスムーズに行えるように「獣医師さんに伝えたい情報」も紹介していきます。
猫を早急に動物病院を受診した方がいい状況
以下のチェックリストに1つでも当てはまる状況なら、早急に動物病院を受診しましょう。
処置が遅れると、死に至る可能性もあるので、猫が嘔吐する様子をよく観察してください。
チェックリスト
- 激しく嘔吐している
- 1度に繰り返し嘔吐する
- 嘔吐したあと食欲も低下して元気がない
- 嘔吐する前の動作を頻繁に行う
- 嘔吐物に血が混じっている
- 下痢もしている
- 脱水症状をおこし皮膚に張りがなく目がくぼんでいる
- 数日間、毎日1回以上嘔吐している
- 嘔吐することにより体重が減ってきた
- 嘔吐物に「虫」がいた
- 誤飲・誤食をしたものが中毒症状を引き起こす可能性がある
受診時に獣医師さんに伝えるべき情報と注意点
診察がスムーズに行えるように、以下の情報を伝えられるように準備しておきましょう。
獣医師さんに伝えるべき情報
- 嘔吐した回数
- 嘔吐する症状はいつから始まったのか
- 最後にとった食事から、どのくらいの時間が経過したか
- どんな吐き方をしていたか
- 嘔吐物に入っていた物や色
- 嘔吐したあとの猫の様子
- 下痢・熱・食欲低下など他の症状はあるか
嘔吐物を動物病院に持っていけそうなら、アルミホイルやラップに包んで獣医師さんに見せましょう。
point
ティッシュやキッチンペーパーで包むと嘔吐物を吸収してしまうためNG!
嘔吐物を持っていくことが難しい場合は、写真や動画に撮って獣医師さんに見せると診察がしやすくなります!
嘔吐の頻度を抑えるための予防策

猫は嘔吐しやすい動物ではありますが、頻繁に嘔吐を繰り返すことで、体に大きな負担をかけてしまします。
また、他の病気を引き起こす原因にもなりかねないので「猫の健康を維持するためには嘔吐の頻度を減らすこと」が重要です。
以下の、嘔吐の頻度を減らすための予防策を参考にしながら、猫の健康を守りましょう!
毛玉の予防・ケアを行う
嘔吐物に毛玉が混じっている場合は、猫の体内に被毛が入らないようにすることが大切です。
猫の被毛が体内に入らないようにするには、以下のケアを行うといいでしょう。
ブラッシングをこまめに行う
まずは、猫の抜け毛を減らすために「ブラッシング」をこまめに行いましょう。
ブラッシングが嫌いな猫は、優しく撫でて声をかけながら徐々に慣れさせていきます。
そして「額・腰」など、猫の抵抗が少ない箇所から、ブラッシングを始めるといいでしょう。
ブラッシングの頻度
毛玉の排出を促すフードやケア用品を使用する
体内に溜まっている「毛玉」を嘔吐して吐き出すよりも、便と一緒に排出する方が体に負担をかけません。
そのため、嘔吐物に毛玉が混じっている猫には、消化器官に働きかけて便と毛玉を促すフードやケア用品を使用するといいでしょう。
動物病院やペットショップで販売されているので、1度問い合わせてみることをおすすめします♪
フードの種類や量を見直す
与えているフードが、猫の体質に合わないことが原因で嘔吐してしまっているようなら、フードを他の種類に切り替えてみましょう。
急に違う種類のフードに切り替えると、胃が対応しきれずにさらに嘔吐してしまう可能性もあるので、元々与えてたフードに少しずつ新しいフードを混ぜて与えるようにしましょう。
また「食べすぎ・早食い」が原因で嘔吐している場合は、フードを1日に4回~5回に分けて与えると「嘔吐防止」に効果的です。
フードを少しずつこまめに与えることで、空腹の時間が減らすことができ、胃にかかる負担も軽減されるでしょう。
猫が興味を示しそうな物は置かない
好奇心旺盛な猫は、さまざまなものに興味を示し、興味本位で口の中に入れてしまいます。
そのため「猫の口に入りそうなサイズのもの・猫に害を与えるもの」は、猫の手が届かない場所に片付けましょう。
猫が快適に過ごせる環境をつくる
ストレスが原因で嘔吐している場合は、ストレスに感じている要因を取り除くことが大切です。
猫がストレスに感じる原因は「環境の変化」によるものが多いので、猫が快適に過ごせるように以下のことを参考にしながら、生活環境を整えてあげましょう!
生活環境を整えるポイント
- 猫がリラックスできる場所や空間を作る
- 多頭飼いしている場合は、相性が悪い猫とは生活スペースを分ける
- あまり過度に構いすぎずに、猫のペースに合わせる
- 部屋の模様替えを頻繁に行わない
運動不足もストレスの原因になる場合があるので、おもちゃなどを使用してたくさん遊んであげましょう!
以下の記事では運動不足解消にピッタリな「猫のおもちゃ」を紹介しているので、参考にしてみてはいかがでしょうか?
-

-
参考記事はこちら【愛猫の快適な暮らしのために】おすすめ猫グッズをジャンル別に紹介
大切な家族の愛猫には「快適な暮らしをさせてあげたい!」という飼い主さんも多いのではないでしょうか? 筆者も6歳の猫を飼っており「猫じゃらし」や「猫用ベッド」など、さまざまな猫グッズを購入しました。 そ ...
続きを見る
愛猫が嘔吐した時は正しい対処法をとろう!

おさらい
- 嘔吐する前・嘔吐した時・嘔吐した後をよく観察する
- 嘔吐した直後は食事や水を控える
- 動物病院を受診する時は、できる限り嘔吐物を持参した方がいい
前述したように、猫は頻繁に嘔吐を繰り返す動物です。
しかし、よくあることだからといって、油断していると取り返しのつかない事態になる可能性もあります。
飼い主さんの「的確な判断・処置」が、猫の健康を守るための大事なポイントになるでしょう。
日頃から猫の様子を観察して、異変を感じた場合にはすぐに動物病院を受診してください!