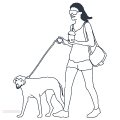人間は刺激物を食べたり鼻をかみすぎると、病気ではないのに「鼻血」が出てくることがよくあります。
しかし、犬は人間とは違い、病気以外の原因で鼻血を出すことはほとんどありません。
そのため、犬が鼻血を出した場合には何らかの「病気・怪我」が潜んでいる可能性があります。
病気・怪我の症状を悪化させないためには「早期発見・早期治療」がとても重要ですが、まずは飼い主さんが適切な対処をする必要があります。
そこで、この記事では「鼻血の原因・考えられる病気」や「病院に行く前にチェックしておきたい項目」について紹介します。
この記事を読んでわかるポイント
- 犬が鼻血を出した時に確認するべき3つのことがわかる
- 鼻血が原因として考えられる病気がわかる
- 鼻血を出した時の対処法と予防策がわかる
【Contents】
愛犬が鼻血が出した時に確認する3つのこと

獣医師さんにスムーズに診断をしてもらうためには「飼い主さんの問診」がとても重要になります。
鼻から血を流している愛犬の姿を見るとパニックになってしまう方も多いですが、まずは冷静に以下の3つの点を確認しましょう。
病院に連れて行く前に確認すべき点
- 鼻付近からの出血ではないか
- どちらの鼻から出血しているのか
- 鼻血以外の出血はないか
1.鼻付近からの出血ではないか
愛犬の鼻に血がついていると「鼻血」だと思ってしまいがちですが、もう1度鼻付近をよく確認してみましょう。
実際は鼻血ではなく、鼻付近の「皮膚が炎症」を起こし出血しているという場合も多くあります。
万が一、鼻付近に皮膚トラブルがある場合は、病院での診察をスムーズにするために、他の身体の箇所に同じような病変がないか確認しましょう。
また、鼻付近の「傷」が原因で出血している場合には、清潔なタオル・ガーゼ・ティッシュで出血している箇所を優しく押さえてあげましょう。
傷が深い場合や出血がおさまらない時には、動物病院を受診し適切な処置を行ってもらうことをおすすめします。
point
皮膚トラブルの原因が分からない時は「アレルゲン」を調べてもらいましょう。
2.どちらの鼻の穴から出血しているのか
「鼻血は片方から出ているのか」もしくは「両方の鼻の穴から出ているのか」は、病気を診断する際の重要な判断基準になります。
片方から出ている場合、全身性疾患の「血液凝固疾患」の可能性は低く、外傷の可能性が高いといわれています。
病院が嫌いな子は、鼻を触られるとパニックになり抵抗してしまう場合もあるので、家で確認してから受診するようにしましょう!
3.鼻血以外の出血はないか
鼻血以外に、身体の他の箇所から出血していないか確認しましょう。
全身性疾患の血液凝固疾患の場合、鼻血の他に全身の皮膚や粘膜からの出血、尿や便に血が混じるなどの症状がみられます。
上記のような症状がみられた場合には、早急に動物病院を受診しましょう!
鼻血の原因として考えられる病気

犬が鼻血を出した時には、さまざまな「病気や怪我」をしている可能性が考えられます。
ここからは、鼻血の原因になり得る病気や怪我の症状などを詳しく紹介していきます。
鼻の中の怪我
鼻を強くぶつけて骨折したり、喧嘩やじゃれ合いなどによって、鼻の中に傷を負ってしまうと鼻血を出すことがあります。
傷の深さや範囲によりますが、怪我を負った場合には突然大量に鮮血が流れ出てくるので、ビックリしてしまう飼い主さんも多いでしょう。
また、鼻の中に何らかの異物が混入した時も、鼻から出血する場合があります。
異物が混入した時は、鼻血だけではなく異物を出そうと「くしゃみ」を繰り返すことが多いので、くしゃみが多い場合は異物混入を疑いましょう。
異物が原因で鼻血が出ている場合には「CT検査→鼻腔鏡で確認→摘出」することができるので、症状が悪化する前に動物病院を受診することをおすすめします。
鼻腔内腫瘍や腎臓病などの重大な病気
鼻血の他に「くしゃみ」を繰り返している場合には「扁平上皮がん」「悪性リンパ腫」「繊維肉腫」などの腫瘍ができている可能性があります。
腫瘍が原因の場合には「くしゃみ」以外に、以下のような症状がみられる場合があるのでチェックしましょう。
腫瘍が原因の場合にみられる症状
- 傷を負っていないのに少量の出血が長期間続く
- クリーム状の鼻水に血が混じっている
- 鼻水の中に血の塊が混じっている
- 顔が腫れて片方の穴から出血する
歯周病
歯肉炎や歯槽膿漏など「歯周病」が悪化してしまうと、歯の根元から鼻の中にまで菌が侵入して炎症が広がり、大量の膿性の鼻水と鼻血が出るようになります。
歯周病を放置すると体内にまで細菌が広がるので、早急に動物病院を受診するようにしましょう。
また、シニア犬は「歯槽膿漏」になりやすくなるので、普段から「デンタルケア」をしっかりと行うことが大切です。
以下の記事では「デンタルケアの方法」や「デンタルケアグッズ」を詳しく紹介しています♪
デンタルケアのことを詳しく紹介している記事はこちら
-

-
参考記事犬用おすすめ歯磨きグッズを徹底比較!選び方や利用者の口コミも紹介
犬の歯は「健康のバロメーター」といわれています。 そんな大事な歯を守るために役立つ「犬用歯磨きグッズ」には、さまざまな種類があることをご存知でしょうか? 今回は、歯磨きグッズの種類や特徴、実際利用して ...
続きを見る
薬疹
薬疹とは塗り薬などの外用・飲み薬・注射などの薬物を投与した後に皮膚や粘膜におこるアレルギー反応のことです。
薬剤を投与してすぐに症状が起こることもあれば、何度か投薬をした後に副反応が現れる場合があります。
犬の薬疹の発生率は「約2%」とかなり低い可能性ではありますが、以下のような症状がみられる場合には「薬疹」を疑いましょう。
薬疹の症状
- 鼻血
- 剥奪性皮膚炎
- 蕁麻疹
熱中症
熱中症の初期症状は、呼吸が荒くなったりよだれを垂らすなどの症状ですが、重症になると「鼻血や湿疹」などの症状がみられます。
以下の犬種は熱中症なりやすい傾向にあるので注意しましょう!
熱中症になりやすい犬種
- 短頭種(パグ・フレンチブルドッグ・チワワなど)
- 子犬
- シニア犬
- 肥満体型の犬
熱中症を予防するために、夏場はエアコンなどを使って「室温は26℃」湿度は除湿器などを使って「50%程度」を目安に保つようにしましょう。
犬が鼻血を出した時の対処法

人間が鼻血を出した時には、止血したり安静にするなどの対処法がありますが、犬が鼻血を出した場合にはどのような対処を行えばいいのでしょうか?
ここからは、犬が鼻血を出したときの対処法について紹介していきます。
ティッシュでの止血はNG!
人間の場合、鼻血が出るとティッシュを穴に詰めて止血する人が多いでしょう。
しかし、人間と同じように犬の鼻にティッシュを詰めてしまうと、鼻腔内を傷つけたり窒息の原因になりとても危険なので、絶対にやめましょう。
家で行える犬の鼻血の止血方法はないので、むやみに鼻には触れず早急に動物病院を受診するようにしてください。
鼻血を出したら速やかに動物病院で検査を!
前述したように、犬が鼻血を出しても飼い主さんが止血してあげることはできません。
少しでも鼻血を出した時には速やかに動物病院を受診した方がいいのですが、状況判断に迷った時には
- 今は動かさず安静にさせた方がいいのか
- すぐに病院へいくべきなのか
- どのような応急処置ができるのか
などを、動物病院に電話をして確認するといいでしょう。
日頃からできる2つの予防策

ここからは、日頃からできる「2つの予防策」について紹介していきます。
2つの予防策
- デンタルケアを怠らない
-
殺鼠剤をまいた場所に連れて行かない
1.デンタルケアを怠らない
前述したように、歯周病が悪化すると「鼻水」「鼻づまり」「鼻血」などの症状を引き起こすことがあります。
そのため、日頃からデンタルケアを行い、歯垢や歯石を溜めないようにすることが大切です。
家でデンタルケアを行うことが難しい方は、獣医師さんにお願いしましょう!
2.殺鼠剤をまいた場所に連れて行かない
ネズミを殺すクマリン系の抗凝固性殺鼠剤には、ワルファリンや血を止まりにくくする成分が入っています。
そのため、犬が散歩中に舐めたりしてしまうと、鼻血・吐血・下血などの症状を引き起こしてしまいます。
また、殺鼠剤そのものを食べていなくても、薬がついている草などを舐めてしまうと中毒症状がおこる可能性も・・・
そのような状況を避けるためにも、薬剤でネズミを駆除しているような場所は避けて散歩するようにしましょう!
犬にとって「鼻血」は大きなストレスを感じる

犬の鼻には「匂いを感じ取る」「呼吸をする」「細菌などを撃退する」などの役割があります。
とくに、犬の嗅覚は人間の1000倍~1億倍も優れているといわれており、匂いを嗅ぐことで多くの情報を得ています。
しかし、鼻から出血してしまうと嗅覚が鈍り、周囲の情報を得ることができなくなってしまい、犬は不安やストレスを感じてしまいます。
大きなストレスを抱えてしまうと、食欲不振や問題行動に繋がることも珍しくないので、症状が悪化する前に動物病院を受診しましょう。
日頃から愛犬の行動を観察しよう!

おさらい
- 家で鼻血を止血することは難しいので早急に動物病院を受診する
- 鼻血を予防するために日頃からデンタルケアを怠らない
- 診察がスムーズに行えるように「3つの確認事項」をチェックしておく
犬が鼻血を出す時は「病気・怪我」が原因になっていることがほとんどです。
犬は鼻血や鼻水が出ると舌でペロっと舐めてしまうので、気づくまでに時間がかかるという飼い主さんも多いでしょう。
しかし、そのまま鼻血を放置しておくと症状は悪化し、愛犬は苦しい思いをし続けることになります。
そのような状況を避けるためにも、日頃から愛犬の行動・仕草をよく観察して、異変を感じたら早急に動物病院を受診しましょう!